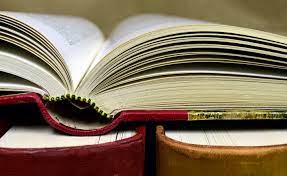独禁法の基本知識についても、基本的には城戸が執筆を担送しますが、他の弁護士が書く場合もあるかもしれません。その場合は()で執筆者名を表示してもらうなどするかもしれません。
基本知識の解説、第一段は、独禁法を学ぶための基本テキスト(基本書)です。
独禁法はまず、どの本から始めたら良いか、迷う人もいるかと思います。
弁護士でも、何が実務か見失う等躓いてしまうことも少なくないように感じられます。
おすすめの順番は、実務的な運用を中心にまず基礎を固めることです。
菅久修一、品川武他『独占禁止法』(商事法務)は、公取委実務に親和的なベーシックなテキストとして推薦できます。
人によって合う・合わないもありますので、幕田英雄『公取委実務から考える独占禁止法』(商事法務)も比較して購入を検討されると良いでしょう。
学問的な考え方の真髄を学びたい人は、川浜・瀬領・泉水・和久井『ベーシック経済法』(有斐閣)が面白いです。ただ、学問的に相当高度な議論を最小限の記述量で表現していますので、実際に理解できるのは他の書物等での勉強が進んだ段階かもしれません。
通説的な立場の最高峰は、おそらく泉水文雄『独占禁止法』(有斐閣)かと思われます。実務家は手元に1冊置いておくと良いですね。
白石忠志先生の本は薄いので若手弁護士が手を出しがちですが、通説・実務へのアンチテーゼ的な立ち位置として理解しても良いのではないかと、個人的には思います。ベテランの方には、平井先生の債権総論や新堂先生の民事訴訟法のような、といったらイメージしやすいでしょうか。通説・実務をきちんと理解していないと、どこが「すごいこと」を言っているのか、等よくわからないかと思われます。
通説や実務とは問題の切り口が違ったりするので、そうした鋭い分析(「頭いい!!」との感動)、再構成に興味がある人は、とても面白く新鮮な視点を得ることもできるかもしれません(「確かにその問題はそのように考えた方がしっくりくるな」といった感じになるかも)。
白石先生の本で学ぶのなら、より説明が厚い太い本の方がおすすめです。分厚いですが、情報量が多いというより、説明がより丁寧な気がします。